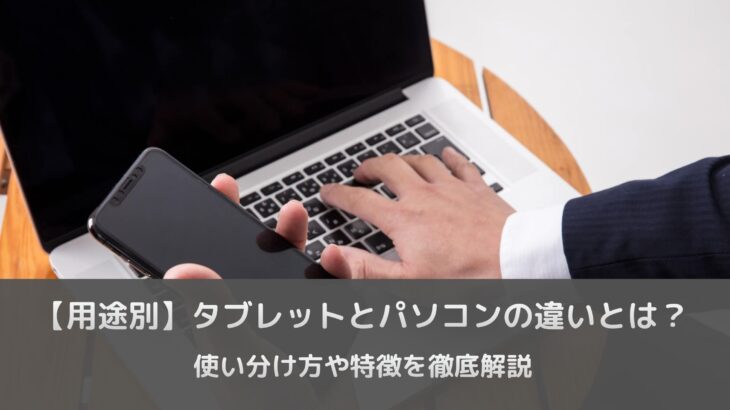「タブレットは便利そうだけど、わざわざ買うほどのメリットはあるの?」
「スマホとタブレット、2台も持つ意味はある?」
タブレットを使おうか検討しているものの、上記のように悩んでいませんか?
タブレットには、スマホやノートパソコンとはまた違った活用方法があります。シーンに合わせて使い分けたり、スマホ・パソコンと一緒に使ったりすることで、効率よく快適に作業ができるようにもなるでしょう。
この記事では、タブレットを使うメリットやデメリット、スマホとの違いなどを紹介していきます。
タブレットのメリット
タブレットは持ち運びやすく操作性もよいため、さまざまな場面で役立ちます。タブレットの主なメリットについて、それぞれ確認しておきましょう。
持ち運びやすい
タブレットは軽量で薄く、キーボードやマウスなどの周辺機器も必要ないため、手軽に持ち運べます。
多くのモデルが500g以下程度の重さで、サイズは7~12インチほどなので、バッグの中に入れてもかさばりません。
タブレットはスマホよりも画面が大きいものの、ノートパソコンと比べるとコンパクトです。そのため、「資料や動画を見たいけどノートパソコンを持ち運ぶのは重くて大変」という場合には、タブレットが適しています。
タッチ操作がしやすい
タブレットの大きな画面は、指でのタッチ操作がしやすいのが特徴です。スマホではやりづらいような細かい操作も、タブレットなら誤操作せずにできるでしょう。
特に、Webサイトの細かいボタンや文字をタッチしたり、文書を作成したりと、画面の細部を操作したいときは大画面が便利です。
Webサイトのスクロールや地図の拡大縮小などもスムーズで、高齢者や子どもでも簡単に操作しやすいという利点もあります。
また、イラスト制作や手書きメモを取る際には、タッチペンを併用することで紙に書くような感覚で作業が可能です。
タブレットのデメリット

タブレットは便利なアイテムですが、使い方次第でデメリットを感じる場面もあります。タブレットはどんなときに使いづらいのかを知っておきましょう。
細かな作業や入力がしづらい
タブレットはタッチ操作が基本のため、キーボードやマウスを使うパソコンと比べると、細かい作業には向いていません。長文の文章入力や細かいデザイン編集など、普段パソコンを使っている人ほど操作のしづらさを感じるでしょう。
特に、タッチ操作のみではカーソル移動やコピー&ペーストといった基本操作がしづらいため、作業効率が落ちる場合があります。ExcelやWordなどを使った作業も、細かい部分が選択しづらいので誤操作が発生しやすいです。
あくまで、「スマホよりも細かい操作はしやすいが、パソコンよりはしづらい」という点に注意しましょう。
重い作業には向かない
タブレットはパソコンほどの高いスペックはないため、高度な動画編集や3Dモデリングといった処理の重い作業には向いていません。アプリの同時起動や複数のタスクを並行して行うと、動作が遅くなる場合もあります。
特に、RAM容量が少ないモデルでは、アプリの切り替え時などに動作がもたつくことがあります。画面がカクカクしてスムーズに操作できないなど、ストレスを感じるでしょう。
高性能なタブレットもありますが、それでもパソコンと比較すると性能面では劣ります。タブレットでどんな作業をするのかよく考えて、パソコンと使い分けるのがおすすめです。
スマホとタブレットの主な違い
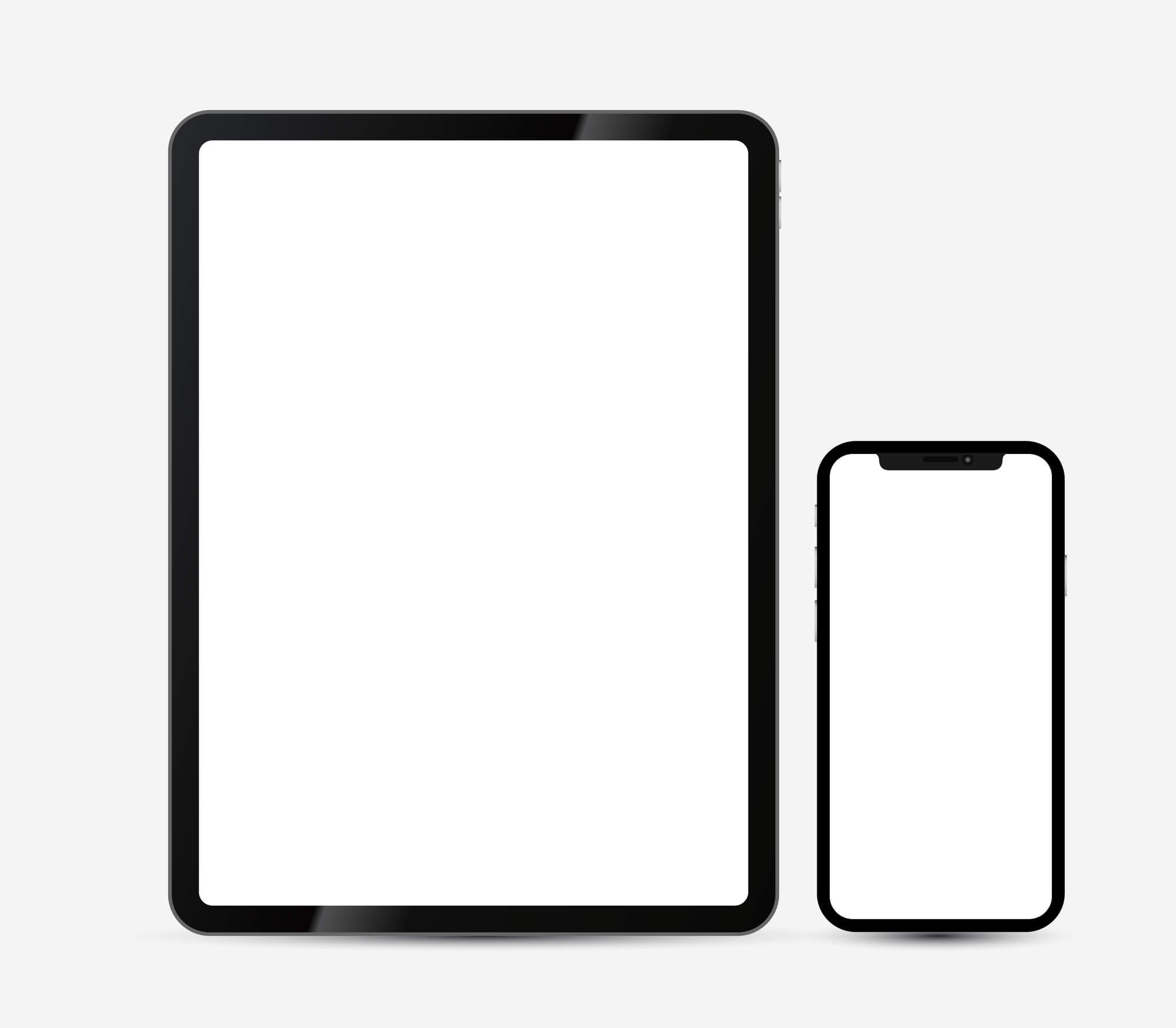
スマホとタブレットは似たような使い方ができるアイテムです。それぞれの違いを理解しておくことで、うまく使い分けられます。
画面の大きさ
スマホの画面サイズは一般的に5~7インチ程度ですが、タブレットは7~12インチほどが主流です。
タブレットは画面が大きい分、動画視聴や電子書籍の閲覧がしやすく、目の負担も軽減できます。特に、電子書籍やPDFの閲覧ではタブレットの大画面を生かせるので、拡大せず快適に読めるのが利点です。
一方で、片手で操作しやすいのはスマホであり、持ち運びの手軽さを重視する場合はスマホのほうが適しています。メッセージや軽いネットサーフィン程度であれば、スマホサイズでも十分です。
電話機能
スマホは標準で通話機能を搭載していますが、タブレットは通話機能を搭載していないものがほとんどです。ただし、LINEやZoomなどのアプリを使えば、タブレットでもインターネット通話は可能です。
通話機能を搭載した一部のタブレットは、SIMカードを契約してモバイルデータ通信ができる状態であれば、スマホと同じように通話できます。キャリアや格安SIM事業者と契約すれば、電話番号の取得が可能です。
電話をするだけであれば、軽くてコンパクトなスマホがおすすめです。ビデオチャットで顔を見ながら話す際には、タブレットの大画面を活用できます。
月額料金
Wi-Fiモデルのタブレットであれば、通信回線の契約をせずに使えるため、月額料金はかかりません。一方でSIMフリータブレットを選び、SIMカードを契約して使うなら、スマホと同様に通信費用が発生します。
SIMフリーの場合は自由に回線事業者を選べるため、格安SIMなどを利用すれば通信費用を抑えられるでしょう。
SIMカードの契約は通信費用が発生しますが、Wi-Fi環境がなくてもネットを利用できます。反対に、SIMカードを契約しないのであれば通信費は発生しませんが、Wi-Fi環境下でしかネットを利用できません。
スマホとタブレットを2台持ちするメリット

タブレットを購入すると、スマホと合わせて2台のデバイスを持つことになる人も多いでしょう。2台持ちするメリットについて紹介します。
作業の効率が上がる
タブレットの大画面を生かしながらスマホと使い分けることで、作業効率が上がります。例えば、スマホで資料やデータなどを見ながら、タブレットで入力するといった使い方が可能です。
どちらか片方だけだと、何度も画面を切り替えながら作業を進めなければいけないため、無駄が多くなります。2画面あればパソコンのデュアルディスプレイのように使えるため、作業のストレスも減らせるでしょう。
バッテリーの消耗を抑えられる
タブレットとスマホを併用することで、それぞれのバッテリー消耗を抑えられるのも利点です。特に、重いアプリを使ったり、長時間の作業をしたりすると、バッテリーは早く減ってしまいます。
外出時、スマホのバッテリーが切れないか心配しながら使った経験をお持ちの方も多いでしょう。
充電用にモバイルバッテリーを持ち歩く方もいますが、充電の手間や時間を考えると、タブレットを持つのがおすすめです。
万が一の予備になる
スマホとタブレットどちらかが使えない場合でも、もう一方があればすぐに対応できるため、予備として持っておくと安心です。
例えば、スマホのバッテリーが切れたときやトラブルで使えなくなったときでも、タブレットがあればメールやメッセージアプリで連絡が取れます。
仕事中や緊急の連絡が入るかもしれない場面では、万一に備えてスマホとタブレット両方を持っておくのがおすすめです。
スマホとタブレットを使い分けるには

スマホとタブレットはできることが似ているため、どう使い分けるのがよいのでしょう。上手な使い分け方について紹介します。
作業や資料の確認はタブレット
画面サイズの大きなタブレットは、文書作成や編集作業、プレゼンテーション資料の確認、ウェブサイトの閲覧など、情報を視覚的に捉えたい場面で使うのがおすすめです。
スマホでは見づらい細かな文字や図表も、タブレットであれば快適に確認できます。外出先での屋外作業や、複数人で資料を共有しながら検討する際などにも、タブレットの大きな画面は活躍します。
近くにいる人と一緒に画面を確認しやすいので、人に何かを説明するようなシーンでは便利に使えるでしょう。
連絡だけならスマホ
電話やメッセージなど、連絡手段として使うだけならスマホで十分に事足ります。タブレットは通話ができない場合が多く、スマホよりも大きいため、連絡用に持ち運ぶには適していません。
また、Wi-Fi専用タブレットは、Wi-Fi環境がなければネットに接続できないデメリットがあります。誰かと連絡を取りたい場合でも、Wi-Fi環境があるところまで行かなければいけないので、緊急の連絡には使えません。
連絡手段として持っておきたいだけであれば、わざわざタブレットを持ち運ぶことはせず、スマホだけ持って出かけても問題はないでしょう。
タブレットを便利に活用する方法

タブレットはスマホとノートパソコンの中間のような特徴があるので、うまく活用すればさまざまな使い方ができます。
キーボードを使って入力作業を楽にする
Bluetooth対応の外付けキーボードを用意すれば、ノートパソコンのように文字入力ができます。特に長文を打つ場合は、画面タッチでは入力しづらいのでキーボードがおすすめです。
フルサイズのキーボードであれば、パソコンで作業する感覚とほとんど同じように使えるため、効率よく進められてストレスもかかりません。
また、キーボードの中には、持ち運びに適した折りたたみ式のモデルや、タッチパッドを搭載したモデルもあります。少し荷物は増えますが、マウスも併せて用意するとさらに作業が楽になります。
パソコンのサブモニターとして使う
タブレットとパソコンを接続すれば、パソコンのサブディスプレイとして活用できます。PCモニターを2枚設置しなくても手軽にデュアルモニター環境をつくれるため、パソコン作業が多い方におすすめの使い方です。
ワイヤレス接続に対応したアプリを利用すれば、配線なしで簡単にデュアルディスプレイ化できます。
また、パソコンと接続しなくてもタブレット単体でネットは使えるので、資料を表示したり調べものをしたりするだけなら、デュアルモニター化しなくてもサブのモニターとしては十分に活用できます。
紙の資料を取り込んでペーパーレス化
タブレットのカメラ機能や専用アプリを使って、紙の資料を電子化できます。ペーパーレス化を進めることで、書類管理が楽になり、スペースの節約にもつながるので便利です。
また、クラウドストレージと連携すれば、どこでも資料を閲覧できるようになります。クラウドに置いておけばいいので、ほかの人と共有するのも簡単です。
説明用の資料などを人に見せる際にも、タブレットさえあればいいので準備も楽です。紙の資料のように、印刷して持っていく手間もありません。
お店の決済端末や企業の勤怠管理に使う
タブレットは、店舗での決済端末(POSレジ)として活用されたり、従業員の出退勤を記録・管理するシステム端末として利用されたりするケースも増えています。専用のアプリ・システムをインストールすることで、さまざまな業務効率化につながるでしょう。
例えば飲食店であれば、各テーブルに持って行って決済をしたり、従業員と話しながらシフト調整したりと、タブレット一つでさまざまな業務をカバーできます。
売り上げデータを集計したり、データを分析したりできるシステムなどもあり、それらをタブレットで分かりやすく一括管理できるのも特徴です。
プレゼンや商談で使う
タブレットは、プレゼンテーション資料や商品カタログなどを表示するのに最適です。大画面で見やすく、タッチ操作でスムーズに資料を切り替えられるため、効果的に情報を伝えられます。
軽量で持ち運びやすく、スマートな印象を与えるため、商談や打ち合わせのような場面でもおすすめです。タブレットに必要な情報をすべて入れておけば、荷物も少なく身軽に動けます。
Web会議に使う
タブレットにはカメラとマイクが内蔵されたモデルも多いため、Web会議でも手軽に利用できます。外出先でも、スムーズにオンラインでのコミュニケーションが可能です。
もしカメラやマイクが内蔵されていない場合でも、外付けのWebカメラやマイクを接続することで対応できる機種もあります。
オンライン学習に使う
タブレットは、電子書籍や動画教材など、オンライン学習に必要なコンテンツを快適に閲覧できるため、学習ツールとしても便利です。
持ち運びやすく、場所を選ばずに学習できるため、通勤・通学中や休憩時間などのスキマ時間を活用できます。タッチ操作で書き込みができるアプリを利用すれば、紙のノートのように使うことも可能です。
まとめ
タブレットは、大画面かつ持ち運びにも便利なので、ビジネスからプライベートまでさまざまなシーンで活用できます。スマホよりも見やすく、ノートパソコンよりもコンパクトなので、それぞれのいいとこ取りをしたようなデバイスです。
もちろん、スマホやノートパソコンと一緒に使えばさらに便利な使い方もできます。2台持ち、3台持ちしている人も多く、うまく使えば作業の効率化や負担の軽減につながるでしょう。
また、スマホやノートパソコンがトラブルで使えない場合にはタブレットで代替できることもあるため、サブ機として持っておくのもおすすめです。
ただ、性能が高いほど端末代金が高額になり、データ通信を利用するならSIMカードの契約も必要なため、タブレットの導入を迷っている方もいるでしょう。まずはレンタルサービスを利用して、お試しで使ってみるのがおすすめです。